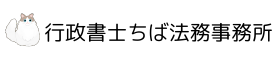古物営業の許可申請は、古物・風俗専門行政書士である当事務所にお任せください
当事務所は、古物営業に特化した行政書士事務所です。これから古物営業を始めたい皆様の様々なご要望にお応えし、スムーズな開業をサポートいたします。
古物営業のサポート
・個人または法人として古物営業を始めようとしている方
・事業拡大を目指し、古物営業を開始したい方
・開業準備に時間をかけられない方
・古物営業法の解釈が難しいと感じている方
無料相談のご案内
当事務所では、無料相談を実施しています。お客様のご指定の場所に伺い、丁寧にご相談に応じます。
お客様が考えている営業形態や経営方針についても、しっかりとサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。0176-52-7132受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ
古物営業許可の申請手続きの流れ

まずはご連絡ください。
ご連絡いただければ、打ち合わせの場所、日時を決定いたします。打ち合わせ場所は、当事務所、お客様ご指定場所、zoom等ご指定場所で実施したします。

打ち合わせ
経営形態・経営方針、開業予定日等を確認し、開業に必要な書類、開業までのスケジュールを作成します。お打ち合わせは無料です。


確認・公官庁提出
申請書類をご確認後、お客様の事務所所在地管轄の警察署へ提出します。標準的な審査期間は約40日となっております。

営業許可
営業許可が下りましたら古物営業が可能となります。
古物商の許可取得について
古物営業法の目的
中古品やリサイクル品等の古物を取引するときのルールを定めたものが古物営業法となります。古物の売買等には、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、それら犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれがあるため、法令等により各種規制を設けることで、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復出来る社会を維持していくことを目的としています。
古物とは何
それでは古物とは何でしょうか?
古物とは、一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といい、古物営業法第2条により定義されています。つまり一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(いわゆる「新古品」)も対象物となります。また、古物をメンテナンスして新しく見せかけた物も同様です。
具体的には古物営業法施行規則第2条により、次の 13 品目に分類されています。
| 項目 | 説明 | 例 |
| (1)美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
| (2)衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
| (3)時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
| (4)自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | その部分品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
| (5)自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | タイヤ、サイドミラーなど |
| (6)自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 空気入れ、かご、カバー等 |
| (7)写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
| (8)事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
| (9)機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
| (10)道具類 | (1)から(9)まで、(11)から(13)までに掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
| (11)皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
| (12)書籍 | ||
| (13)金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
取り扱うものが、上記13品目に該当する場合には、古物営業許可が必要となります。
古物営業とは
古物の売買等を業として行う場合に、許可が必要となります。業として行うというのは、利益を出そうという意思があり、ある程度継続性があることをいいます。
つまり、古物から収入を得ようとして買い取ると古物商許可が必要となります。なお、店舗を設ける場合はもちろん、店舗を設けずにインターネット上での売買でも許可が必要となるので注意が必要です。
古物を取り扱う営業全体を総称して「古物営業」と呼び、古物営業はさらに「古物商」、「古物市場主」、「古物競りあっせん業者」に分けられています。
①古物商
古物を自らまたは他人の委託を受けて売買又は交換する営業のことです。具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋などのリサイクルショップのことだと考えてください。もちろん、インターネットを利用して取引する場合も含みます。
②古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業です。
③古物競りあっせん業者
インターネットオークションが行われるシステムを提供し、システム提供の対価として出品者・入札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収している業者をいいます。
古物営業許可が必要なケース
以下に当てはまる場合は、古物営業許可が必要となります。ただし、不要なケースもありますので、一度ご相談ください。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品などを売る
- 持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をいただく(委託販売)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
- ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
2.古物商等の許可取得要件の確認をいたします(古物営業法第4条)。
古物商・古物市場主を営もうとする人は、営業所が所在する都道府県公安委員会の許可を受けることとなります。また、古物競りあっせん業者は、都道府県公安委員会に届出をすることとなります。
《許可を受けられない場合・・法第4条》
次の欠格要件に該当している人は、許可申請をしても許可を受けることができません。申請した場合は、申請手数料(19,000円)の還付がいただけなくなります。
(1)破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(5)第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第8号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
(7)営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
(8)法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの